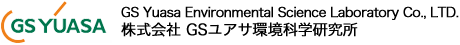大気汚染防止法の一部を改正する法律
一部の規定を除き、令和3(2021)年4月から施行されます。
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等※1への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。
規制対象建材を拡大
- 石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大※2します。
- 石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準を設けます。
事前調査の信頼性の確保
- 事前調査の方法を法定化します。(書面調査、目視調査及び分析調査)
- 「必要な知識を有する者※3」による事前調査の実施を義務付けます。(施行:令和5年10月~)
- 一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等※4が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。(施行:令和4年4月~)
- 事前調査に関する記録を作成し、一定期間保存※5することを義務付けます。
罰則の強化·対象拡大
- 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されます。
- 下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
- 都道府県等による立入検査の対象を拡大します。
作業記録の作成·保存
- 「必要な知識を有する者※6」による取り残しの有無等の確認を義務付けます。
- 作業記録の作成·保存※7を義務付けます。
- 作業結果の発注者への報告を義務付けます。
- ※1 都道府県、大気汚染防止法の政令市など
- ※2 新たに規制対象となる石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材に係る工事については作業実施の届出の対象から除外。
- ※3 建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
- ※4 元請事業者または自主施工者
- ※5 解体等工事終了後3年間保存
- ※6 石綿作業主任者、※2の事前調査の必要な知見を有する者
- ※7 解体等工事終了後3年間保存
改正の概要
①規制対象となっていない石綿含有成形板等(レベル3)の不適切な除去により石綿が飛散
・<規制対象>全ての石綿含有建材に拡大
②不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし(見落とされた現場の都道府県等による把握が困難)
・一定規模以上等の建築物等について石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の都道府県等への報告の義務付け
※ただし、環境省と厚生労働省が連携し電子システムによるコネクテッド·ワンストップ化。制度開始時より運用。
・調査方法を法定化(必要な知識を有する者による書面調査、現地調査等)
・調査に関する記録の作成·保存の義務付け
①短期間の工事の場合、命令を行う前に工事が終わってしまう
・隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等の直接罰の創設
・下請負人を作業基準遵守義務の対象に追加
②不適切な作業による石綿含有建材の取り残し
・作業結果の発注者への報告の義務付け
・作業記録の作成·保存の義務付け(必要な知識を有する者による作業終了の確認)
【建築物や工作物を解体・改造・補修する際は事前調査が義務化】
解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認する必要があります。
(1)大気汚染防止法に事前調査の方法が規定されました。(新法第18条の15第1項)
①設計図書その他書面による調査※1
②現地での目視による調査
③分析による調査
(2)建築物の事前調査は、必要な知識を有する者に実施させる必要があります※2~5
【義務付け適用】令和5(2023)年10月1日~(新法第18条の15第1項及び第4項、新規則第16条の5)
①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)※一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能。
※なお、義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」として認められています。
【事前調査流れ】
①設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に石綿が使用されているか否か、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用した調査を行います。
②現地で各部屋·部位の網羅的に確認します(書面調査との相違等を確認)。
書面調査のみで「石綿使用なし」と判断してはいけません※1
③同一材料毎に代表試料を採取·分析し、石綿含有の有無を判定します。
※1 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や、ガスケット等猶予期間を設けられていた一部製品の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。
※2 工作物については、調査者等による事前調査の実施は義務付けられていません。
※3 石綿含有建材の種類が多岐にわたるような大規模建築物や、改修を繰り返し石綿含有材料の特定が難しい建築物は、特定調査者や一定の実地経験を積んだ一般調査者に調査を依頼してください。
※4 義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を実施させてください。
※5 分析調査は、厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省令第277号)に依頼してください。
【自主施工者である個人による事前調査について】
解体等の工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く)が床、壁、天井等への家具の固定のための孔あけ等、排出·飛散される粉じんの量が著しく少ない軽微な工事のみを施工する場合は、必ずしも「必要な知識を有する者」に事前調査を実施させる必要はありません。ただし、個人であっても作業基準の遵守義務等は適用されますので、専門家による事前調査をお勧めします。
(3)一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告しなければなりません。
【義務付け適用】令和4(2022)年4月1日~(新法第18条の15第6項、新規則第16条の11)
[規模要件]
・建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
・建築物の改造·補修、工作物の解体·改造·補修:請負金額の合計が100万円以上
※工作物は環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)、金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。
[報告事項]
調査対象の建築物等の概要、解体等工事の期間、建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か(該当しないと判断した場合はその根拠)、調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項等
[報告の方法]
新たに整備する電子システム ※石綿障害予防規則の報告と共通のシステム
(4)事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。
【記録事項】(新法第18条の15第3項及び第4項、新規則第16条の8)
【届出が不要な作業についても作業計画を作成する必要があります】
特定粉じん排出等作業を行う際は、届出対象特定工事ではない場合でも作業開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいて特定粉じん排出等作業を行うことが、新たに作業基準に位置付けられました。
【作業計画に記載する事項】(新法第18条の14、新規則第16条の4第1項)
・特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人であってはその代表者氏名
・特定工事の場所
・特定粉じん排出等作業の実施期間
・対象特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の方法
・対象となる建築物等の概要(構造·階数·延べ面積等)·配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
・概ね発注者への報告事項となります。
【隔離等をせずに吹付け石綿の除去を行う等、 正しい方法で作業が実施されていない場合は、 直接罰が適用されます】
吹付け石綿及び石綿含有耐火被覆材等の作業について、行わなければならない措置及び方法に違反があった場合には、作業基準適合命令を介さずに直接罰則が適用されることになります。
【特定建築材料の除去等の方法】(新法第18条の19、新規則第16条の12~14)
・除去
(1)かき落とし、切断、又は破砕することなく取り外す方法
(2)除去を行う場所を他の場所から隔離し(前室も設置)、除去を行う間、JIS Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん·排気装置を使用する方法
(3)(2)に準ずるものとして環境省令で定める方法(例:グローブバッグ)
・当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理
囲い込み又は封じ込め(吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する石綿含有断熱材等の囲い込み等(切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、作業を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、隔離した場所においてJIS Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん·排気装置を使用する方法)
集じん·排気装置が正常に稼働していること、作業場及び前室が負圧に確保されていることの確認頻度が強化されます。
【作業基準】(新法第18条の14、新規則第16条の4第6号·別表第7の4の項下欄)
【石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等を除去する際の作業基準が新設されました】
石綿含有仕上塗材の除去に独自の作業基準が設けられました。
【作業基準】(新法第18条の14、新規則第16条の4第6号・別表第7の3の項下欄)
・石綿含有成形板等はセメント等で固形化されているため、通常の使用では石綿は飛散しにくいですが、劣化している場合や除去時に切断·破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあります。
・けい酸カルシウム板第1種は他の成形板に比べ、飛散性が高いため、切断·破砕等を行う場合は湿潤化に加え養生が必要です。
【作業基準】(新法第18条の14、新規則第16条の4第6号·別表第7の4の項下欄)
【石綿の除去等作業完了後は、確認及び発注者への報告が必要です】
取り残しや不適切作業による石綿の排出及び飛散を防止するため、作業の記録および適切に作業が行われていること及び取り残しがないことの確認が作業基準に位置付けられました。 確認した結果は 発注者に書面で報告するとともに記録を作成し、一定期間保存する必要があります。
・作業の記録
特定工事の元請業者等又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定工事が終了するまでの間保存する必要があります。
【作業基準】(新法第18条の14、新規則第16条の4第3号)
・作業が計画に基づき適切に行われていることの確認
特定工事の元請業者等は、下請負人が作成した記録により作業が計画に基づき適切に行われているか確認し、記録を作成·保存する必要があります。
【作業基準】(新法第18条の14、新規則第16条の15第4号)
・取り残し等の確認
元請業者等は、除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されているか否かについて、「知識を有する者」に目視で確認させる必要があります。
【作業基準】(新法第18条の14、新規則第16条の4第5号)
・特定粉じん排出等作業の結果の報告等
特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告するとともに、作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存しなければなりません。
自主施工者も作業に関する記録の作成·保存が必要です。
【特定粉じん排出等作業の結果の報告等】(新法第18条の23第1項)
【書面で報告する事項】(新規則第16条の15第1項)
【記録事項】(元請業者:新法第18条の23第1項、新規則第16条の15第2項、(自主施工者:新法第18条の23第2項、新規則第16条の16)
【記録の保存】(新法第18条の23、新規則第16条の16)
【罰則の対象が拡大されます】
下請負人も罰則等の対象となります。
特定工事の元請業者及び自主施工者に加え、下請負人も作業基準の遵守義務等の対象となりました。このため、特定工事の元請業者や請け負った特定工事の全部または一部を他者に請け負わせるときは、その者に対して特定粉じん排出等作業の方法等を事前に説明する必要があります。
【下請負人に適用される違反等と罰則】
・除去等の方法の義務違反3月以下の懲役又は30万円以下の罰金(新法第18条の19、第34条第3号)
・作業基準適合命令違反6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(新法第18条の21、第33条の2第1項第2号)
(過失の場合は3月以下の懲役または30万円以下の罰金(新第33条の2第2項))
このほか、罰則はないものの、作業基準の遵守義務(新法第18条の20)があります。
[その他下請負人に拡大される規制等]
・自治体が行う報告徴収及び立入検査の対象となります(対象は特定工事の施工分担範囲)。
[元請業者等が事前に下請負人に説明しなければならない事項]
(新法第18条の16第3項、新規則第16条の11)並びにその使用箇所及び使用面積
報告及び立入検査の対象拡大
対象者に下請負人を加えるとともに、営業所、事務所等その他の事業場を立入検査の対象に加えます。報告事項も規制強化にともない追加されています。
【立入検査の対象】(新法第26条第1項)
【報告の対象】
新法第18条の19に定める方法により行わない場合の理由、新規則第16条の7
各号に掲げる事項(解体等工事に係る説明事項)
【災害時に備え、建築物等に石綿が使用されているか確認しておくことが重要です】
近年、災害の甚大化により、損壊した石綿使用建築物等から石綿が飛散するおそれが高まっています。
このような状況を踏まえ、国及び地方公共団体は連携して平時からの建築物等における石綿使用有無の把握に向けた取組を促進していきます。
【国の施策】(新法第18条の24)
【地方公共団体の施策】(新法第18条の25)
※地方自治体が条例を定めて規制をしている場合がありますので、当該作業を行う場所を管轄する都道府県、市町村にお問い合わせください。
詳細については、下記のホームページをご覧ください。
①法例改正の資料等掲載ページ
https://www.env.go.jp/air/post_48.html
②建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html